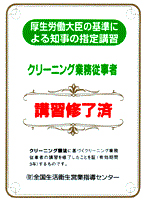【研究室コラム】クリーニング事故の原因と責任
全国857か所(令和5年4月1日現在)の「消費生活センター」へのクリーニングに関する相談件数は減少傾向にあります。1990年代後半には年間11,000件を超えていました(全体の約6%、第一位)が、2023年には1,600件(全体の約0.2%、第十一位)と減少しています。
消費生活センターへのクリーニングに関する相談件数
-1-1-300x132.jpg)
クリーニングに関する相談件数減少の要因は、クリーニング取次店数の減少(ピーク時の約1/2)やクリーニング需要の減少(ピーク時の約1/3)が考えられます。また、1990年から開始され、義務付けられた「クリーニング師研修」や「クリーニング業務従事者講習」の成果とも考えられます。
| クリーニング師研修(略) クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、(業務に従事した後1年以内、その後は3年を超えない期間ごとに)クリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。(クリーニング業法第8条の2)
クリーニング業務従事者講習(略) 営業者は、その業務に従事する者に対し、(従業員5人に1人以上、クリーニング所開設後1年以内に、3年を超えない期間ごとに)当該業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。(クリーニング業法第8条の3)
|
しかし、クリーニング業の現場では、お客様とのクリーニング事故に関するトラブルは数多く存在しています。クリーニング事故の原因は何であり、どうしてトラブルになるのでしょうか?
| クリーニング事故の原因 |
クリーニング事故の原因を追究し、再発防止するため、原因調査を行います。
| クリーニング事故の原因調査
➀事故製品の「取扱表示」や処理された「クリーニング方法」、事故までの経緯を確認する。 ➁事故製品の色の変化や形態変化など、外観を観察、さらに顕微鏡で事故部位を拡大観察、状況によってブラックライト(紫外線)下でも観察、より詳細な事故の情報を得る。 ③事故の部位に付着、残留する成分を抽出、そのpH、汗や薬品類などの有無を調べる。 ④事故原因が推測されれば、確証を得るため、事故原因と同じ条件で再現試験を行う。 |
クリーニング事故の原因調査の結果、主なクリーニング事故は、「色の変化」、「破損」、「その他」に分類され、その原因が製品の「染色堅ろう度不良」や「物性(物理的な性質)不良」によるものか、クリーニング業者の「不適切なクリーニング処理」によるものか、お客様の「着用状況」や「保管状態」によるものかが推測され、その事故の責任が、「メーカー」、「クリーニング業者」、「お客様」のどこにあるのかも推測されます。
主なクリーニングでの事故の原因と責任の所在
| 内容 /責任の所在 | お客様(着用中、保管中) | クリーニング業者 | メーカー |
| 色の変化 | ・紫外線
・汗 |
・不適切な処理
(汚染、移染) |
・染色堅ろう度不良
・表示不適切 |
| 破損 | ・虫害
・着用摩擦 |
・不適切な処理 | ・物性不良
・表示不適切 |
| その他 | ・着用摩擦による
(毛玉、毛羽、白化・・・) |
・不適切な処理による
(収縮、伸長、硬化・・・) |
・物性不良による
(摩耗、滑脱、毛玉・・・) |
クリーニングでの事故で多いのは「色の変化」で、不適切なクリーニング処理による真の「クリーニング事故(汚染や移染など)」もありますが、局所的な色の変化は製品の「染色堅ろう度不良」やお客様の「不適切な着用や保管」に起因した、「クリーニングに伴う事故」になります。
| 染色堅ろう度 |
染色堅ろう度とは、染色された繊維製品が洗濯、摩擦、日光、汗など、様々な外的要因による、色落ちや色移りのし易(やす)さ(又はし難(にく)さ)、変色のし易(やす)さ(又はし難(にく)さ)などを示す指標です。
この指標は、JIS規格などの試験方法に基づいて「染色堅ろう度試験」を実施し、色の変化を数値(級数)で表して評価します。数値が大きいほど良い結果を表し、等級は5級が最も高く、1級が最も低いです(ただし、耐光に関しては、8級が最も高い)。一般に、衣類の染色堅ろう度が4級~5級であれば、色落ちや色移りし難く、変色し難い品質で、安心して着用や洗濯ができます。
主な染色堅ろう度試験は以下のとおりです。
| ・洗濯堅ろう度:家庭での洗濯による色落ちや色移りの評価(JIS L 0844)
・摩擦堅ろう度:摩擦による他の生地へ色移りする程度を評価(JIS L 0849) ・耐光堅ろう度:日光(紫外線)による色あせする程度を評価(JIS L 0842、JIS L 0843) ・汗堅ろう度:汗による色落ちや色移りを評価(JIS L 0848) ・ドライクリーニング堅ろう度:ドライクリーニングによる色落ちや色移りを評価(JIS L 0860) ・水堅ろう度:水による色落ちや色移りを評価(JIS L 0846) |
染色堅ろう度の評価の数値が低い(3級以下)繊維製品は、お客様が着用中に色あせや色落ちなどの変退色(変色と退色)が起こる可能性があります。特に、外出時の日光の紫外線による色あせ(耐光堅ろう度不良)や、着用中の汗による色落ちや色移り(汗堅ろう度不良)などが起こる可能性があります。
紫外線の経年変化(気象庁)
-1-3-300x167.jpg)
紅斑紫外線量:紫外線の影響で、特に皮膚が赤くなる(紅斑)現象を数値化したもの
国内の紫外線量は1990年以降、長期的に増加傾向にあります。気象庁によると、1年間に地表に届く紫外線の量は増加傾向が続いていて、増加率は10年当たりで4.6%になるということです。以前からオゾン層の破壊により紫外線が増加したと考えられましたが、近年はディーゼル車の規制やクリーン自動車の普及によって大気中のチリや汚染物質が減って大気がきれいになったことで、紫外線が増加したとも考えられています
紫外線量が増え、各地で猛烈な暑さが続き、真夏日の日数も最多更新している昨今、紫外線や汗による変退色が増えていないのか、気になるところです。
| クリーニングに伴う、変退色事故の責任 |
衣類をクリーニングに出す際、お客様は衣類に紫外線が長時間あたっていたことや汗が付着していたことを気にせず、衣類が部分的に変退色していることに気づいていない場合が多く、クリーニング店でも変退色を見逃して、クリーニング処理してしまうことがあります。クリーニングすると汚れが除去され、シワが伸びるため、着用中の紫外線や汗に起因する変退色が目立つようになります。そのため、クリーニングにより色が変わったと、トラブルになることがあります。
染色堅ろう度の評価の数値が低い(3級以下)繊維製品の事故の場合、責任の所在は、その製品を製造・販売したメーカーにあります。反対に染色堅ろう度に問題がなく(4-5級)、過度の着用(紫外線や汗の影響が大きい)により変退色が起きていたのであれば、責任の所在はお客様になります。
しかし、染色堅ろう度の試験データがないメーカーやその請求に応じないメーカーもあり、客観的な染色堅ろう度の評価ができず、クリーニング処理に伴って判明した変退色事故の原因と責任がどこにあるのかは不明で、お客様とクリーニング業者とのトラブルになります。
着用中の変退色の事故によるトラブルを防ぐには、クリーニング店での受付の際、お客様と店員の両者で、製品に変退色が起きているのか否かを相互に確認することが必用です。あるいは、クリーニング工場での処理をする前に変退色を発見していれば、処理前にお客様に連絡することでトラブルを防げるかもしれません。また、素材メーカーやアパレルは責任をもって、染色堅ろう度に問題がない製品を提供することが求められます。
以上
無断転載はお断りしております。本記事をご利用の際は、ポニークリーニングへお問い合わせください